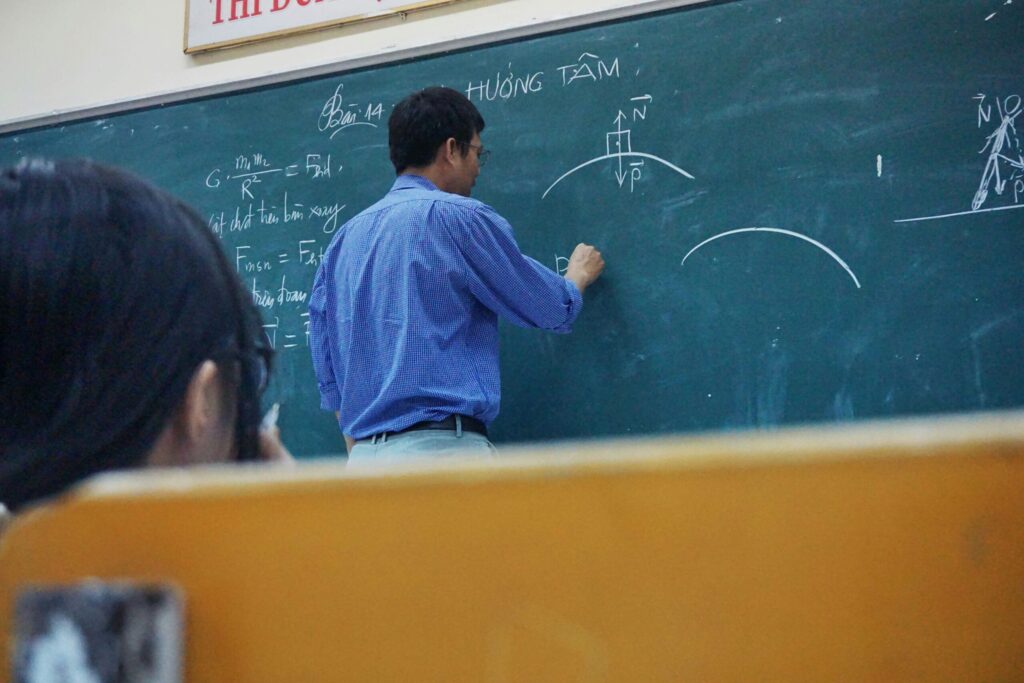
こんばんは。mokumokuです。
みなさん、「生成AI」使ってますか。
世の中は、「大AI時代」に入っています。
日々、テクノロジーは進化し、AIとの付き合い方、仕事の在り方が問われています。
今回は、「AI時代に必要な能力と教員の役割」について書いていきたいと思います。
はじめに
みなさんもご存知の通り、文部科学省から
”初等中等教育段階における生成AIの利活用についてのガイドライン”
が公表されています。
つまり、生成AIの存在は学校教育の現場にも大きな変化を与えるインパクトがあるということです。
教員として生成AIについて正しく理解することはもちろん、効果的な活用法を知る必要があります。
教員としての自分の基本的な考えは、
・AIが得意なことはAIに任せる。人にしかできないことに注力すべき。
・子どもたちに、人間ならではの生きるための力と、AIとの正しい付き合い方を身に着けさせる。
この2つです。
教員としてできること、しなくてはならないことは何か。
ホスピタリティを高める。

教師という仕事は、AIに代替されにくいとされています。
その理由の1つが、「ホスピタリティ」です。
ホスピタリティとは、相手に安心感や喜びを提供し、深い思いやりを持って接する精神的な態度や行動を意味します。
AIは、「情報整理」「反復作業」「効率化」「要約」などが得意です。この辺りは、人間がかなわないところもあります。作業的なタスクが得意なのです。
では、実際の教室に「AI先生」がいたらどうでしょう。
テストの点に応じて、個人個人に的確にアドバイスします。
評価の基準に沿って、日々の生活の中で子どもを誉めます。しかも、一日何十回でも、全員平等に、疲れなく、毎日することができます。
これだけ聞くと、
「AIに勝てるところあるの?」
と思ってしまいそうになりますよね。
でも、AIにはできない、私たち教員だからこそできることがあります。
それは、子どもの「なんとなく」の空気感を感じ取ったり、いつもと「ほんのわずかに違う」声のトーンや表情に気付き、声をかけたりすることです。
これは、AIにはできないこと。教師という仕事がAIに代替されにくい理由の1つです。
「ホスピタリティ」は何もAI時代だから大切なことではありません。教師として身に着けるべきものであることは以前から変わりません。
それにより磨きをかける必要があるということです。
日々の子どもたちの様子を丁寧に見とること。微妙な変化に気付くこと。言葉を吟味し、その子にどんな声で、どんなトーンで話すのかを深く考えること。教室を安心できる居場所にすること。
これを意識して積み上げていく必要があります。
我々教員にしかできないことに、磨きをかけていきましょう。
3つの資質能力を育むための授業を「レベルアップ」する。
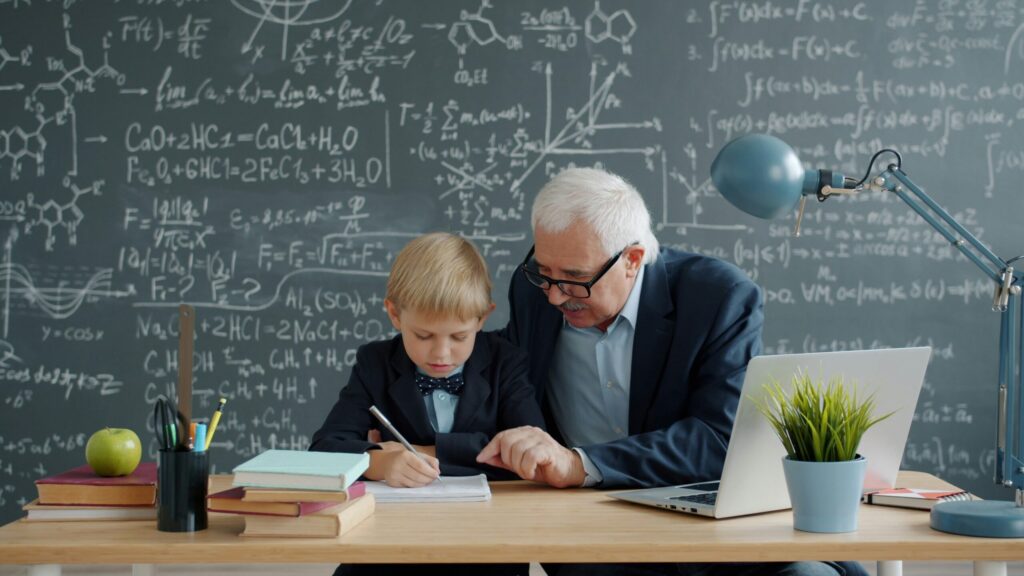
生成AIは便利である分、使い方によってもたらす効果に雲泥の差が出ます。
効果的に活用するためには、
・AIについての正しい理解
・自分が求めているものを出力させるためのプロンプト(指示文)を書く力
・自分の求めていたものと出力された結果を分析し、判断する力
・意欲や向上心を持って、結果を基に創意工夫する態度
これらが必要であると考えます。
上記を基に考えると、今までの授業で求められていた力が”より”必要になっていると感じませんか?
的確なプロンプトを書くためには高い言語化能力が必要です。どんな条件で、どのような完成イメージで、誰に対して、、、というようなことを、分かりやすく表現する力が必要になります。プロンプト次第で、出力結果は大きく変わってきます。
結果を基に自分の頭で考え、判断し、次につなげていく力が必要です。生成AIが出力した答えが正しいものだとは限りません。ハルシネーション(間違い)を起こす可能性は十分あります。盲目的に信じず、あくまで参考にし、自分の力で練り上げていく必要があります。
「どうすればよくなるかな」「どうして思い通りにならないのかな」と考える意欲や向上心が必要です。これがないと、
「AIがこう言っているから。」
というような、他責思考に陥りやすいと考えます。言えば「AIのいいなり」です。
こうならないためにも、意欲や向上心は必須のものであると考えることができます。
生成AIとの付き合い方について考えれば考えるほど、3つの資質能力を育成する必要性が見えてきます。
日々の授業の中で
・問いを自分で作る力
・答えのない問いに対して、自分の頭で考える力
・主体的に学ぼうとする力
これらを育成していく必要性が今まで以上に増しました。
教員の腕の見せ所です。僕も日々奮闘しています。一緒に頑張っていきましょう!
「AIリテラシー」を身に着ける。(大人も子どもも)

まずは教員自身がAIを積極的に使ってみることが大切です。
プライベートでも仕事でも(使い方は区別しなければいけませんが)とにかく使ってみる。
その体験を通して子どもたちに伝えていくのが、自然な流れかと思います。
・ハルシネーションを起こす可能性がある。(間違いやもっともらしい嘘を出力する現象)
・最後の責任は自分が取る必要がある。
特にこの2点は、大人も子どもも正しく理解しておく必要があります。
授業での活用例
僕も積極的に活用しようとしている最中なので、活用例を1つご紹介します。
内容が少し難しい物語文ありますよね。
これを生成AIに簡単に要約してもらいます。
「小学校低学年でも分かるように、物語を要約して。」
すると、本当に分かりやすくまとめてくれます。
ここで必要なのは、それをそのまま児童に伝えるわけではないことです。
この要約はあくまでAIの出力。そのままではなく、内容を見直して、時には言葉をつけ足したり省いたりします。AIが絶対に正しいわけではないのです。
あとは、物語の挿絵などをもとに説明することで、大まかな内容を児童に伝えることができます。
長い物語の文章を読んですぐ理解できる児童もいます。
ただクラスの中には、長い文章を読むことも聞くことも苦手で、そもそも学習の入り口に立つのが億劫な児童もいるでしょう。
そのような場合に有効です。
これはあくまで一例で、絶対に正しい使い方だとは思いません。
「教員なら物語を分かりやすく自分でまとめられるだろ。」
と言われればそうかもしれません。
でも自分は、日々忙しい中で、AIを活用することで時間を捻出することに意味があると思っています。
AIが得意なことはAIに任せましょう。
これからの教育に必要なこと。
ここまで述べてきたように、生成AIはとても便利ですが、あくまで補助ツールとして活用する必要があります。
優秀な同僚、もしくは部下と一緒に仕事をするような感じです。
・意見を出してもらう。
・足りない視点からの意見はないか考えてもらう。
・たたき台を作ってもらう。
そのためにAIを活用します。
そもそもの「問い」を立てたり、ここから意見を考えたりするのは人間のやることです。
「自分の頭で考え、判断し、その責任を持つ。」
この態度を忘れないこと。重要です。
そして子どもたち。
「言われたことを言われたとおりにやる」
指示したことをただ遂行するのはAIがやることです。
変化の激しい時代を、臨機応変に対応していける人材を育成しなければなりません。
AIについての正しい理解があれば、AIを味方につけ、仕事の内容をより改善していくことができるでしょう。
これからの時代を生きていく子どもたちにとって、
・AIリテラシー
・自分で問いを立て、自分で考え判断し、自分で責任を取る
この力が必要不可欠です。
この力の育成のためのサポートを、教員はしていかなくてはなりません。
終わりに
『NVIDIA』というアメリカのAI企業の創業者であり最高経営責任者である、『ジェンスン・ファン』さんは、こんなことを言っています。
「AIが仕事を奪うのではありません。AIを使った人間が皆さんの仕事を奪うのです。」
なるほどと思いました。
AIは便利である分、「使う人」と「使わない人」との差が大きく開いていくのだと思います。
AIを使う→時間を捻出する→その時間で、より人間にしかできないことをやる
このループに入る人とそうでない人では、10年後大きな違いが出てくるでしょう。
「AIに頼る」というよりは、良き相棒として「AIとともに考える」という考えが必要ではないでしょうか。
今目の前にいる子どもたちは、自分たちの子どもの時代よりもはるかに予測不可能な未来を生きていかなくてはなりません。
教員である自分は子どもたちに何をしてあげられるのか。今回の記事を基に少しでも考えていただければ幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
明日も「もくぶれ」していきましょう!
おやすみなさい。
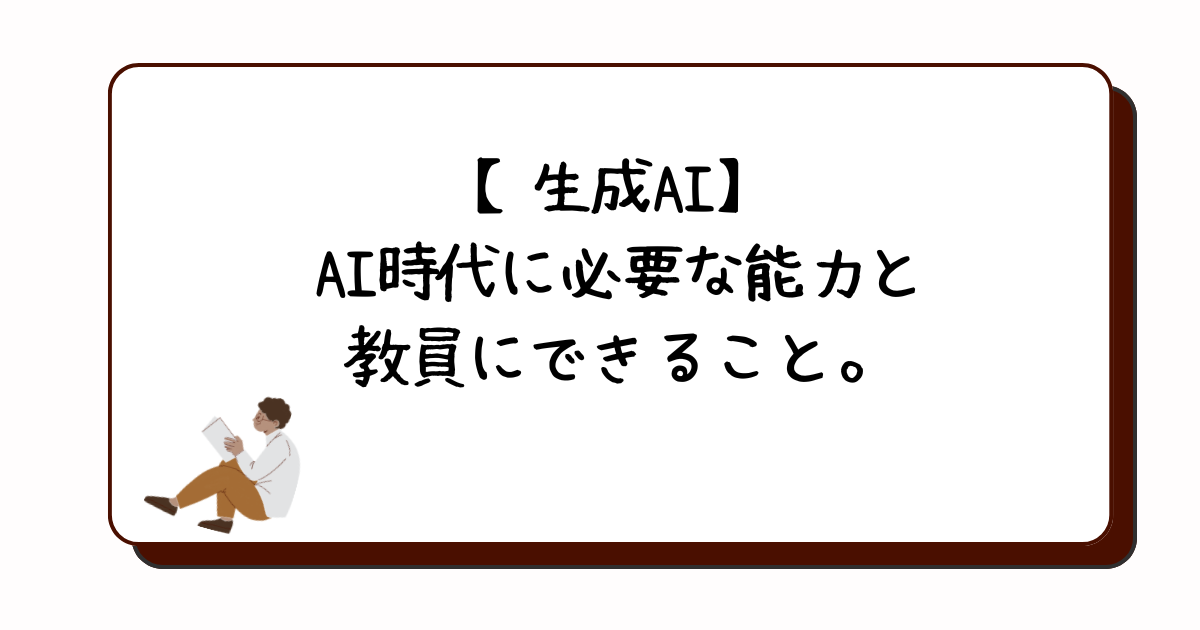


コメント