こんばんは。mokumokuです。
今回は「幸せになる勇気」を読んで感じたことを書いていきたいと思います。
本書は「嫌われる勇気」の続編「勇気の二部作の完結編」とされています。
「嫌われる勇気」の書評もしております。以下のリンクからぜひご覧ください。
→【書評 嫌われる勇気】大切なのは「いま、ここ」を生きること。
「嫌われる勇気」を読んだとき、思いっきり魂を揺さぶられた僕です。本書もとても読むのが楽しみでした。
構成は前作と同じ。青年と哲人の対談形式で話が進んでいきます。
ところで皆さん、タイトルに違和感ありません?
「幸せになる勇気」
幸せになるために「勇気」がいるの?どういうこと?
読んで納得しました。
すべては「信じる勇気」から始まるのです。
始めに
教師をしている人に読んでほしい
どんな人にとってももちろん学びの多い本です。その中でも、教師を仕事にしている方には前作も含めてぜひ読んでほしい。
というのも今作は、「青年が教員として「アドラー心理学」の考えを実践した結果の不満を哲人にぶつける」という構成だからです。
「あなたに教わった通りにやったのに全然ダメだった!」
「アドラー心理学のは結局のところ宗教ではないか。」
青年に足りなかったものは何なのか。読み進めていくと分かります。
そして、教師としての自分を振り返りながら読んでみてください。
これでもかというくらい、揺れます。
尊敬とは

「尊敬する」とはどういうことでしょうか。
「その人の優れているところに憧れる」
僕は何となくこんなイメージを持っていました。実際このような意味でつかわれる場面が多いかと思います。
本書の中では、「教育の入り口は尊敬である」とされています。
そして、哲人は尊敬についてこう語っています。
「尊敬とは、人間の姿をありのままに見て、その人が唯一無二の存在であることを知る能力のことである。」
これは、「エーリッヒ・フロム」という社会心理学者の言葉を引用しています。
教育者である自分たちがまずしなければいけないこと。それは、目の前にいる子どもたち一人ひとりを尊敬することです。
できることやできないことに目を向けるのではない。ただ「ありのまま」を認めること。そこから始まるのです。
子どもを尊敬する。僕が具体的に取り組んでいるのは「真剣に話を聞くこと」です。
話を聞いてくれないって、自分のことを軽く見られていると誰でも感じますよね。
「子どもが言っていることだから」
というような態度は必ず子どもに伝わると思います。
だから一人の人間として、対等な立場で、話を聞く。
どんな思いがあるのか、どうしたいのか、どうなりたいのか。
教員として、また親としても大事にしたい。
本書を読んで改めて感じさせられました。
問題行動の5段階
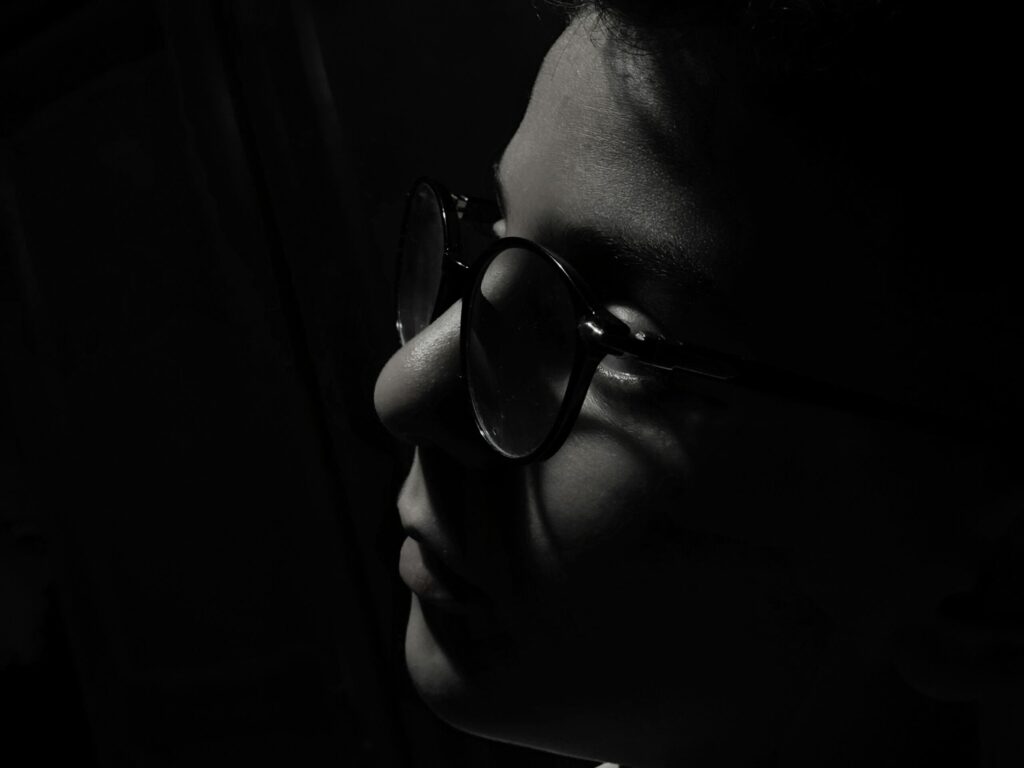
教師として非常に学びが多い部分でした。
ここでは、子どもが起こす問題行動とその「目的」について述べられています。
問題行動には5つの段階があり、徐々にエスカレートしていくという捉え方です。
①称賛の欲求
とにかく「褒めてほしい」という思いから、大人や教師が褒めてくれそうな良い行動をします。
一見良いことのようにも思いますが、本書では問題行動として挙げられています。
②注目喚起
褒められようと頑張っても結果が出なかったり、褒められなかったりという経験から、「注目喚起」の行動へと移っていきます。
なんでもいいからとにかく目立ちたい。注目を集めたいという段階です。
いいことをしても目立てないので、いたずらをしたり、泣いてみたり、という行動に出ます。
③権力争い
教師に反抗したり、不従順だったりといった行動がみられます。
逆らうことで、自分の力を証明しようとする段階です。
現場でも感じるときがあります。
「なぜこの子はここまで反抗的なのだろう。」
どう対処しようか悩むときもありますよね。
このときの対処の仕方として大切なのは相手と同じ土俵に乗らないことだとされています。
少しでも嫌な顔をしたり、叱責したりすると、その子にとって「認めてもらえた」というサインになってしまう可能性があるからです。
④復讐
権力争いの中でも認められなかった子どもはどうするか。
復讐の段階に入ります。
自分を認めてくれない相手に対しての復習です。とにかく相手の嫌がることをし続ける段階です。
本書では、「この段階で教師にできることはなく、外部、専門家に頼ることが必要」だとしています。
そして、子どもの問題行動を第3段階までで食い止めることが教師にとっての大切な役割だとされています。
そのためにも、彼らの目的をきちんと理解しなければなりません。
⑤無能の証明
今までのどの段階を踏んでも特別だと認められなかった。何も達成できないなら初めからやらない。という態度が最後の段階、無能の証明です。
とにかく無気力で、目の前にあるすべての課題を拒否する。この段階でも教師にできることはないとされています。
みんな「特別」になりたい
クラスという共同体の中で誰もが特別でありたいと考えています。そんな自分を認めてもらうために問題行動に出るのです。本書では、
「特別でなくてもいい、ありのままの自分でいい」
というメッセージを子どもに伝えられるかが大切だとされています。
我々教師は、つい褒めるか叱るかで考えてしまいがちです。ですがその関りは必ずクラスの中で競争を生んでしまいます。
正直、本書に記されているやり方を貫くのは相当難しいと感じます。それこそ勇気がいる。
ただ、この問題行動についての考え方を現場での出来事に照らし合わせながら読んでいくと、かなり説得力があるのも事実です。
今自分が全てできているとは到底思えません。
ですが、子どもの行動の目的を理解しようとする態度は、明日から始めることができます。
子どもを尊敬し、理解しようとする。
そこから始めてみましょう。
教師として

最終目標は子どもが「自立」すること
「わたし」の価値を、他者に決めてもらうこと。これは依存です。
一方、「わたし」の価値を、自らが決定すること。これを自立と言います。
本書ではこのように書かれています。
集団の中で「特別であること」よりも「これが私なのだ」と認めてあげられることの方が重要なのです。
そのために我々教師にできることは何でしょうか。
信頼関係を構築する
全てはここから始まると思います。
信頼関係のない人に何を言われても響かないからです。
具体的には、まず自分から子どもを信じること。この子には能力がある、自分で選び、決定していく力がある、と心から信じられるかどうかにかかっています。
自分で選んでいるという感覚を持たせる
自分の人生は、日々の行いは、すべて自分で決定するものなのだと教えること。そして決めるにあたって必要な材料――たとえば知識や経験――があれば、それを推奨していくこと。それが教育者のあるべき姿なのです。
これは前作でも語られていた「課題の分離」にもつながっています。子ども自身の課題に教師は介入しない。という態度でいることが大切だと考えます。
おぜん立てしたものを子どもがクリアしていく形の教育では、子どもは「失敗から学ぶ」ということを「学ぶ」ことができません。
自分が選んでしたことであれば、失敗したり思った通りにならなくても、「自分で選ぶことができるのだ」ということは感じることができるでしょう。
他人のせいにしない、ということにもつながります。
「だって先生がそう言ったから。」
「先生が言った通りにしたらこうなってしまった。」
「○○君のせいでこうなった。」
こんな言葉はよく聞かれます。僕はよくこう言います。
「あなたが選んで行動した結果ですよね?」
冷たい言い方のようですが、決めたのは、行動したのはその子自身であるということは事実です。
もちろん、自分が言った通りに子どもを動かそうとして失敗したときにこんなことは言えません。ある程度参考になる情報を示し、余白を残して子どもに伝えます。
子ども自身が「自分で選ぶ」「選んできた積み重ねが今の自分なのだ」と教えることが重要です。
決断を尊重し援助する
子どもたちの決断を尊重し、その決断を援助するのです。そしていつでも援助する用意があることを伝え、近すぎない、援助ができる距離で、見守るのです。
決断を尊重するというのは、ほったらかしにするというわけではありません。
「まずは自分の力でやってみるといいよ。」
「本当に困ったときは、助けることができるから言ってね。」
周りの大人がこのように言ってくれると、子どもは安心して、集中して物事に取り組むことができます。
自分で選んだことなので、責任感も生まれるでしょう。
子どもを信頼し、決断を尊重し、援助する。この流れが子どもの自立を目指すうえで必要になってきます。
僕も今一度、自分の中の教育の在り方を見直していきたいと思います。
幸福に生きるためには

自己中心性からの脱却
「人生の主語をわたしからわたしたちに変える」
本書にはこう書かれています。
もちろん自分自身を大切にしなければなりません。ですが、「わたしの幸せ」ではなく、「わたしたちの幸せ」を目指すべきなのです。
本書では共同体という言葉がたびたび出てきます。人々は必ず何かの共同体の中に所属しています。家族であったり、職場であったり、趣味の集まりだったり、、。
もっと大きく言うとこの世の中も一つの共同体です。
人々は、共同体の中でやらなければいけないことを分業している。その意識が大切です。
自分のことだけを考えるのではなく、自分を含めた周りの環境ごと大切にする。
難しいですよね。
「今日は一日いい日だったな」
って感じるときって、自分と相手がいることが多い気がします。もっと言うと、誰かのためになれたなという感覚があるときです。
クラスの子たちと良い関りができた。同僚の先生と深い話ができて、さらにそれを実践できた。奥さんが「助かった」と言ってくれた。息子が「今日は最高の日だね」と言ってくれた。
どれも「わたしたちの幸せ」です。
終わりに
すべては「信じる勇気」から始まる。
「幸せになるために勇気がいるの?」
という疑問を持ったうえで本書を読みました。
読み終わって思ったのは、幸せは誰かがくれるものではなく、自分の勇気ある行動から始まり、そして歩み続けなければいけないということです。
「信じてもらいたい」
「愛してほしい」
ではなく、まず自分が相手を信じる。愛する。
自分から相手を信じることには勇気がいります。裏切られる可能性も生まれるからです。
でも、まず自分から相手を尊敬し、信じる態度を始めないと、幸福にはなれません。
能動的に。主体的に。相手を信じよう。尊敬しよう。
自分から始めることの勇気を持てた時、幸福に生きるための一歩を踏み出したといえるでしょう。
人として、教師として。
自分は目の前の子どもたちの可能性を信じてあげられているのか。
自分で人生を決められるんだよというメッセージを送ることができているのか。
日々の仕事のことや、子育ての中で問い直すきっかけになりました。
本書の内容をここにすべて書くことはできません。まだまだ心に響いたことはあります。
僕はこの記事を書くにあたってもう一度ざっと読みなおしましたが、新たな発見がたくさんありました。
読み返した自分の人生のタイミングと本書の内容を重ね合わせると、また新たな発見があります。
これも読書の良さですよね。
何度も読みたいおすすめの1冊です。みなさんもぜひ、読んでみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
明日も「もくぶれ」していきましょう!
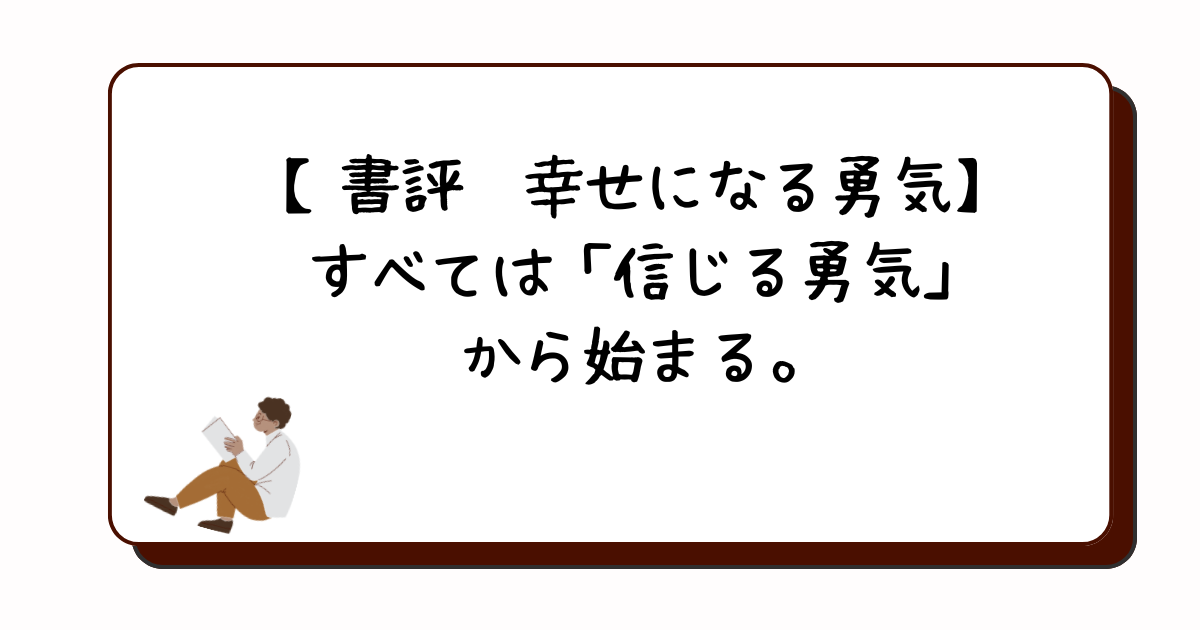


コメント